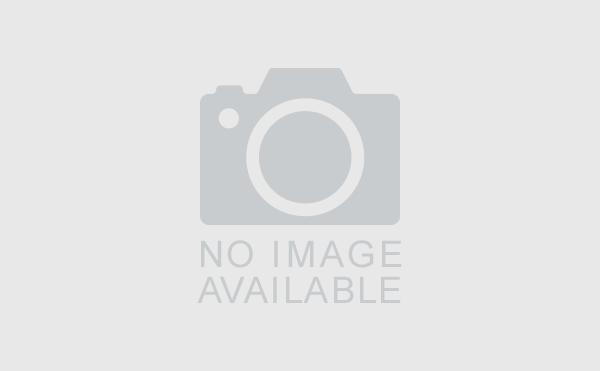みなべ梅対策協議会(会長・小谷芳正町長)は11日に保健福祉センターで梅の機能研究報告会を開き、県立医科大学や和歌山高専などの研究グループがこれまでの成果を発表した。肥満や熱中症などに対する効果のほか「梅の成分のバニリンはがん細胞の増殖を抑制することも分かった」などと説明し、注目を集めた。
研究は平成24年度から大学などの研究機関に依頼して実施。報告会には住民ら約100人が来場し、熱中症、生活習慣病、疲労回復の効果について聴いた。発表は和歌山高専物質工学科の奥野祥治准教授、県立医科大学の河野良平助教、同大学の宇都宮洋才准教授の3人が行った。
奥野准教授は「抗肥満効果・ガン予防効果について」のテーマで発表した。「梅の中に含まれるバニリンとシリンジアルデヒドに脂肪を分解する効果があることが分かった。青梅から梅干しなどに加工することで種の中にある成分が果肉に移ると考えられる」と説明。がん予防効果については胃がんの細胞を使って増殖を調べた結果を報告し、「バニリンががん細胞の増殖を抑制した。周りの健康な細胞は殺さず、がん細胞だけを減らすことができる可能性もあるのではないか」と述べた。
河野助教は「暑熱疲労予防効果について」のテーマで発表。高温度の環境の中にマウスを入れて実験したことを紹介。「マウスに水、食塩、梅抽出成分の3種類をそれぞれ摂取させた。食塩と梅をそれぞれ摂取したマウスは、水だけのマウスに比べて活動量が高かった。さらに梅には疲労の指標となる乳酸を減少させる効果もみられた」などと説明し、「梅干しを継続して摂取することで暑熱ストレスを軽減できると考えられる。仕事や運動の前には1粒から2粒程度食べるといい」と述べた。
宇都宮准教授のテーマは「梅の疲労改善効果について」。筑波大学での研究を基に、梅干しの抽出成分が運動や骨格筋機能に与える影響を説明した。マウスの実験で、運動継続時間が延長する結果が得られ、筋細胞で抗酸化ストレス因子が増加したなどとし、「梅を摂取することで運動能力が向上し、骨格筋機能の維持効果が期待できる。毎日食べることが重要」と述べた。
これまでの研究では、胃がんの原因といわれるヘリコバクターピロリ菌への抑制効果、抗糖尿効果のあるα―グルコシダーゼという物質などを発見している。