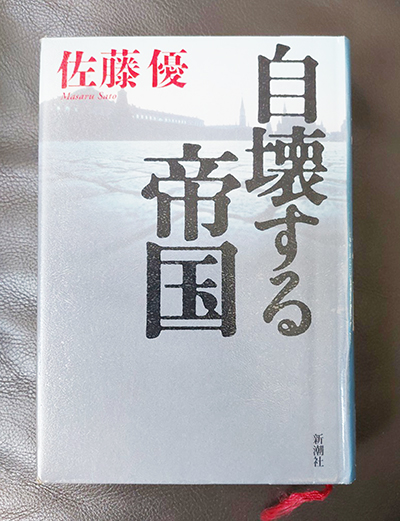
本書は、ソ連崩壊を現地の外交官として見た著者のドキュメントである。
著者は外務省に入省後、ロシア語とソ連事情を英国陸軍語学学校で学び、モスクワへ赴任する。
本著で語られるのはソ連がガラス細工のように脆い帝国であったということだ。
その一例がバルト三国である。エストニア、ラトビア、リトアニアはそれぞれの言語と文化を持った国である。ソ連はその三国をソ連邦の一部としていたが、ゴルバチョフのペレストロイカ以降民族意識が高まり独立へと繋がっていった。象徴的な出来事が「人間の鎖」である。著者は民族雑誌「アトモダ」の編集長アレックスと食事し、尋ねた。
「独立は、具体的には何をやるのか」
「人間の鎖でエストニアの首都からリトアニアの首都まで人間の鎖で繋ぐのだ」
「距離にしてどれくらいある」
「六百キロだ。一人一メートルとして、六十万人が集まれば可能だ」
「そんな六十万人も反ソ運動に繰り出す市民がいるのか」
「できるさ、簡単なことだ」
実際「人間の鎖」は百五十万人、多い時には二百万人にも達した。
またアレックスはこうも言った。
「今のソ連は帝政ロシアの末期に似ている。レーニン、スターリンの動向も帝政側は掴んでいたが革命は阻止できなかった。その状況と今のバルト三国は同じだよ。僕たちはレーニンの手法を逆手にとっているんだ」。
プーチンはそんな時代にソ連のKGB(秘密警察)に生きた人であった。ウクライナ侵攻は、そんな時代のソ連を取り戻そうとしているのだ。(秀)


