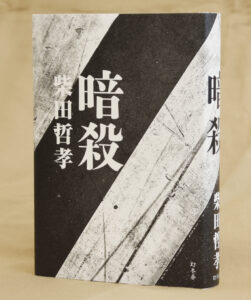本書は二〇〇三年にHⅡAロケットが打ち上げに失敗したことを契機に書かれている。失敗の原因を探るのが本書の狙いである。
本県でも昨年串本町でカイロスロケットが発射されたが失敗している。本書に何かヒントがあるのではと思い紹介したい。
まずは日本のロケット開発の歴史から。
一九五五年、東大の糸川英夫博士のペンシルロケット(全長二三センチ)が最初であった。以後、一九五八年カッパ、ラムダ、ミューと続き一九七〇年L―4となり、これが初の人工衛星「おおすみ」を打ち上げた。気象衛星として有名な「ひまわり2号」は一九八一年NⅡにより打ち上げられた。「1号」の方はフロリダから打ち上げられたので日本のロケットではない。以後ロケット開発は一九八六年HⅠ、一九九四年HⅡとなり、二〇〇一年のHⅡAロケットへと繋がっていく。しかし順調に日本のロケット開発が進んだわけではない。原因の多くが日本政府の科学への無知からきていると本書では書かれる。つまり宇宙開発を担う科学技術庁や文部科学省の大臣等はいずれも文科系であるということである。これに対して中国は、日本の文科省にあたる長官はすべて理工系大学の出身者で、これにより中国の科学進歩は顕著なものとなったという。
串本町のカイロスロケットはベンチャー企業のスペースワンが担っているが、このロケットは群馬県富岡町のIHI(石川島播磨重工)で研究開発されたものだ。
政府もしっかり支援して、カイロスの打ち上げの後押しをして欲しいものだ。(秀)

-212x300.jpg)