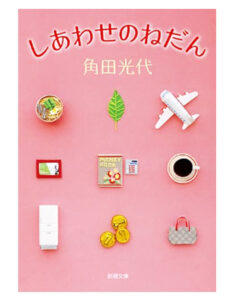日本人で最初に牛乳を飲んだのは飛鳥時代の645年(乙巳の変=大化改新の年)、当地方とも縁の深い有間皇子の父である孝徳天皇だったという。しかしそこから長らくなぜか日本人が牛乳を飲むことはなく、それが変わったのは明治以降のことだ◆大手の牛乳メーカーが先月で瓶入り牛乳の販売を終了したとのニュースを受け、日本における牛乳の歴史を調べてみていろんなことが分かった。明治維新とともに西洋文化が入ってきてから、「西洋人が体格がいいのは牛乳を飲んでいるから」だと滋養強壮のために飲まれ始めた。しかし当初は裕福な家庭か病人のいる家庭だけの贅沢な飲み物で、一般に広く普及したのは戦後、学校給食法で牛乳の提供が定められてからだという◆明治初期の牛乳はブリキ缶を容器とし、ひしゃくでの量り売り。おなじみの牛乳瓶は本紙創刊と同じ昭和3年(1928)から始まった。小学校の給食当番では軽いパン箱を1人、重い牛乳瓶の入ったケースを2人で運んでいたのを思い出す。瓶がぶつかってガチャガチャいう音も懐かしい。瓶のふたは紙製で、突き刺して抜く「牛乳瓶用栓抜き」が前の席から順番に回されていたような覚えもある◆大人になってからも、休日前夜に飲んだ時など、翌朝の冷たい牛乳は甘露であった。一瞬で飲み干してしまうほどおいしかった滋味あふれる味わいに加え、牛乳瓶の飲み口特有の厚みと丸みのあるやさしい触感が癒やしをくれたようにも思う◆効率化の名のもとに社会の均質化が進もうとも、取るに足りないささやかな喜びを含んだある文化の存在を忘れてしまいたくはない。便利さと引き換えに、心の豊かさの度合が下がってしまわないように。(里)