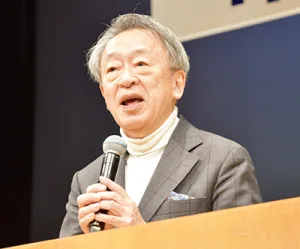農林水産省が昨年8月に公表した日本の食料自給率は生産額ベースで58%となり、過去最低を更新した。食生活の国際化で肉類や加工品の消費が増え、それらの食品を輸入に頼らざるを得ないのが要因だが、国際情勢が危うく、国内で想定外の災害も数多く発生している中、食料自給率が低いということは食糧保障のぜい弱化につながるとされる。自分たちが食べる物は自分たちで、できるだけ生産できるようにしておく方がいいのは言うまでもないが、国の基幹産業である農業一つ取っても、農業者の高齢化、後継者不足などさまざまな難しい問題を抱えている。
御坊市が実施した市内農業者へのアンケート調査でも、今後10年間で農業者の高齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加などが一層深刻化していくことが浮き彫り。御坊・湯川地区をみると、営農者の年齢割合は60代と70代合わせて全体の約65%を占め、後継者が「いない」の回答は73%にも上る。これから先、御坊の農業がどうなっていくのか、数字だけみると非常に不安に感じる。
食料自給率を上げるには地元でとれた新鮮なものを食べて国産の食べ物を応援、ご飯を中心に野菜たっぷりのバランスのよい食事をする、食べ残しを減らすなどがあるそうで、国民一人ひとりが少しでも意識をすれば、食料自給率も上がるし、自身の健康にもつながる。御坊市では近く、農業のあり方をまとめる地域計画策定に向けた「協議の場」を、各地域で設けていく予定。この機会に地域の先人たちが守り続けてきた農業を次世代に着実に引き継ぐためにはどうすべきなのか、あらためて考える機会にしてもらいたい。(吉)