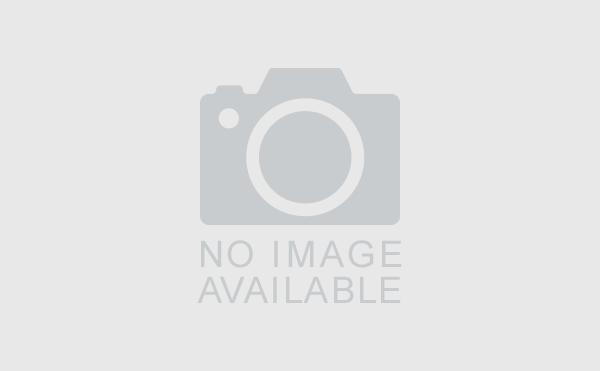国の文化審議会(宮田亮平会長)は19日、日高川町寒川にある寒川家住宅の母屋など7件を国の登録有形文化財にするよう下村博文文部科学大臣に答申した。かやぶき屋根で江戸時代末の建設そのままのたたずまいを残す母屋をはじめとする屋敷構えは、再現が困難で歴史的価値が高く、山里の農村景観にマッチしている点などが評価された。認められれば、日高地方ではみなべ町の大江家住宅母屋に次いで2件目になる。
登録有形文化財は、国宝や重要文化財とは違い、外観を残せば内部の改修を行ってもよい保護制度。登録物件は明治以降に建造、製作されたものが中心だが、江戸時代のものも対象。この日、同審議会文化財文科会の審議、議決を経て、全国で173件が答申された。県内では寒川家住宅7件と、和歌山市の県庁舎本館1棟の合わせて2カ所8件。登録されれば県内の有形文化財は62カ所、168件となる。
寒川家は、寒川 子さん(63)の住居で、所有者は長男の将行さん(37)。住宅のうち、答申されたのは嘉永3年(1850年)ごろ建築の母屋ほか、明治中期の土蔵、大正前期の離れ、後期の小門、昭和前期の石垣、同12年の表門と塀。母屋は、1155平方㍍ある敷地中央に位置し、大きなかやぶき屋根が特徴。建築面積は152平方㍍。床上部分は4つの部屋に仕切られているが、部屋の境が食い違っている珍しい間取り。建築から改変カ所も少なく、江戸時代の大規模農家の姿をそのままに残しており、特に現在まで維持しているかやぶき屋根は貴重とされる。ほか、母屋西側にある落ち着いたたたずまいの離れ、風格がある表門、梅の家紋をかたどった石垣、正面から白い壁を望むことができる土蔵など江戸末期から昭和初期にかけて整えられた屋敷構え全体が周辺の農村景観にマッチしている。 子さんは「とてもうれしくありがたく思います。冬は寒いですが、この季節はとても涼しい住居。今回の登録であらためて大事にしていきたいという思いです」と話している。
寒川家は、6代目が鎌倉幕府からこの土地の地頭職(地頭としての職務・地位)を任じられ、関東から移り住んだとされる旧家。近隣の寒川神社の社家を代々務めている。