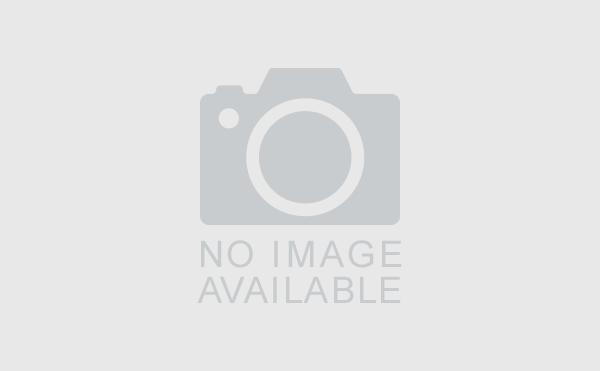昨年9月の台風12号で流域被害を大きくした日高川の河川環境についての研究が21日、 スタートした。 日高川町と立命館大学 (京都市) による共同研究で、 来年3月まで初湯川の椿山ダム湖の土砂の堆積状況や水深の調査、 台風災害時の河川状況のシミュレーションなど行い、 洪水災害のメカニズムを解明する。 町では今後の防災対策や施策の参考材料にしたい考え。
研究を行うのは、 理工学部環境システム工学科の建山和由教授と同都市システム工学科の里深好文教授。 「日高川の洪水氾濫と河床変動に関する研究」 を課題に、 洪水のメカニズムを明らかにし、 今後の洪水対策に生かすことが目的。
具体的にはGPS(全地球測位システム) を備えたラジコンボートを使ってダム下流全域 (町内) の水面下や河床を調査し、 椿山ダム湖の水深やたまった土砂の堆積状況などをみる。 ダム下流域ではボートでの調査結果や台風12号時の流量などのデータを基に、 水害時の日高川の状況をシミュレーション。 数値解析などで河床の変化や川の流れを再現する。 ダム湖では、 上流側の美山漕艇場付近で水深測量や堆積状況などの調査を通してダムの現状を把握。 将来的にはロボットを使ってダム湖の土砂を採取し、 成分を解析。 土砂を効率的に放流する方法なども含めダム機能回復について検討する。 ダムによってせきとめられている河川にとって良質な土砂は下流域に戻し、 ダム建設前の日高川に近づけていきたい考え。 土砂によっては農業に適しているものもあり、 土砂の利用方法についても検討する。 関係者らは、 研究がまとまれば河川水害対策の進歩や川と人との共存のモデルケースになるとしている。
21日には里深、 建山両教授と学生らが同町を訪れ、 漕艇場付近のダム湖で土砂の堆積調査など行った。 里深教授は 「曲がりくねっている日高川は学術的に興味ある研究材料。 川と人間が、 かつて以上のいい関わり合いになれないか研究していきたい」 と意気込み、 玉置俊久町長は 「二度と水害が起こらないよう、 河川環境を解明できれば。 後世の人のために人と日高川の共存方法について提言ができると期待している」 と話している。