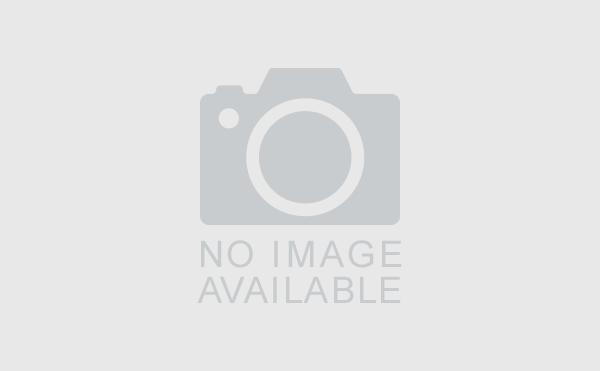先日、印南町体育センターで世界津波の日に合わせた講演会が開かれた。会場はほぼ満席の状態。町民ら約500人が参加し、津波防災への関心の高さがうかがえた。講師は2011年の東日本大震災時に岩手県釜石市で津波から大半の子どもたちが生き延びた「釜石の奇跡」に防災教育で貢献した東京大学大学院情報学環の片田敏孝特任教授。「巨大津波想定に向かい合う防災を考える」をテーマに語った。片田教授の講演を取材するのは2014年以来3年ぶり2回目。約2時間にわたり、みっちり聞かせてもらった。
片田教授は昨年11月22日、津波警報が出された福島県沖を震源とした地震について、避難しなかった人や車で逃げた人がおり、震災から5年半、教訓を生かすのは難しいと実感したそう。過去の津波で生き残った人々が後世のために「高き住居は児孫の和楽 想へ惨禍の大津浪 此処より下に家を建てるな」と残した石碑を紹介。教訓は語り継ぐだけでは限界があるとした。わかりやすかったのは戦争の例え。確かに戦争の悲惨さは語り継がれているが、体験した人と戦後生まれとの認識にはやはり大きな隔たりがある。
防災教育に携わり始めたころ、釜石市では逃げない大人によって逃げない子どもが育まれていたという。100年前の人が石碑に残した思いは3、4世代と続かず、戦争の話は1世代でもピンとこない。「こんな恐ろしいことはない」と片田教授は話し、「10年たてば子どもは大人になり、さらに10年たてば親になる。そして高い防災意識が世代間で継承されれば、災害文化が地域に定着する」と防災教育の重要性を強調。逃げる子どもを育む地域づくりが大切になる。 (笑)