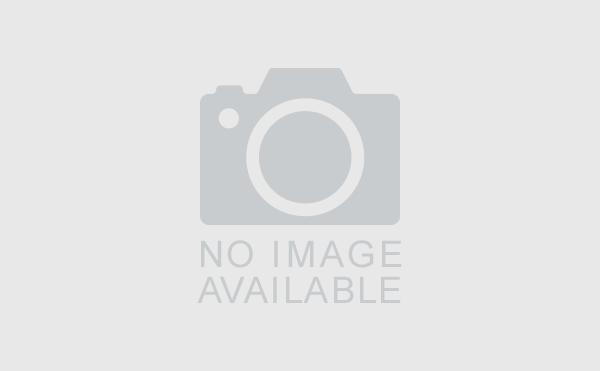先日、東日本大震災の被災地を訪ねる機会があり、福島、宮城、岩手の3県の復旧状況を見て回った。3・11から4年半、津波が街を次々とのみ込み、壊滅的な被害を受けた映像はいまでも忘れられないが、実際に見てきたいまの姿は、まだまだ道半ばではあるが復興へ向けた工事が着々と進んでいた。がれきは目にすることなく、各地区では堤防や道路、住宅地のかさ上げ工事が続き、復旧の速さに驚かされた。被災地を訪れたのは初めてだったが、津波の威力の凄さと、壊滅的な被害を受けてもくじけずに前を向く人たちの情熱を感じた。
一方で、心に刻まれた深い悲しみにも触れた。児童74人、教職員10人が犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校で娘さんを亡くされた男性は、なぜ避難しなかったのか、学校組織の意思決定方法、教職員としてどのように子どもたちを守らなければならないか、教育現場の在り方に一石を投じた。その大川小学校を震災遺構として残そうとする動きと、反対もあることを知った。悲劇を繰り返さないためにも残したい人がいる一方、見るのも辛い、取り壊して人々が語り合う場にしたいという意見もある。誰の考えも間違いではない。それぞれの思いを一つにするのは難しく、負った傷の深さも人によって違う。
もう一つ、堤防建設や避難路整備が充実していたこの東北でこれほどの人的被害が出たのを疑問に感じていたが、岩手県の語り部の女性がいわれていた言葉が胸を突いた。「逃げ遅れたのではなく、ここまで津波はこないだろうと逃げなかったから多くの犠牲者が出た」。近い将来、南海地震の発生が懸念されている我々は、必ず教訓にしなければならない言葉だ。 (片)