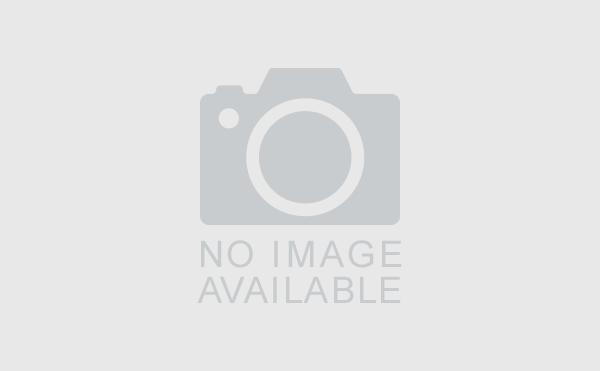「津波避難タワーは万全ではない」。ことし1月に御坊市で行われた防災講演会で群馬大学大学院理工学府の片田敏孝教授も言っていたが、その通り。いくら頑丈なタワーでも100%安全ということはない。だから、御坊市で言うと、津波避難は岩内方面や亀山など高台に逃げるのが基本。そして高齢者や足の不自由な人らが逃げ遅れた場合、タワーという選択肢を選び、被害に遭うリスクを少しでも減らすという考え。行政としてはこれを「タワーにさえ上がれば安全」と住民に勘違いされてしまうことが危険と指摘しており、タワーを建設する際には避難の基本的な考え方も含めた啓発が必要だろう。
そんなタワーについて、市は先月末に完成した薗の施設に続き、新たに薗と名屋の2カ所程度に整備する方針を地域防災計画に盛り込んだ。厳しい財政状況の中で〝英断〟ではないだろうか。名屋の高齢者の中には「遠くまで逃げるのは無理だから、家の中でお経でも上げてじっとしている」と漏らし、避難をあきらめてしまう人がいる。これが近くにタワーが建設されたなら、「逃げてみよう」という気になるかもしれない。また、住民全体の危機意識向上にもつながり、日ごろの避難訓練も一層活発化するかもしれない。タワー建設には事前防災の観点で、そんな効果も期待できるのではないだろうか。
ただ一つ、行政に要望したい。地域防災計画では新たなタワーの整備目標が平成32年度となっている。せっかくの英断も、それまでに災害が起きては意味がない。新年度予算は編成済みだが、年度途中の補正でもいいから早期に着手していただきたい。 (吉)