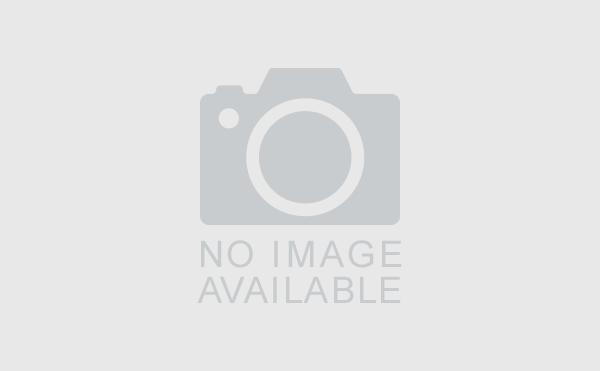市川猿之助御坊公演のための取材がきっかけで歌舞伎の魅力にとりつかれた1999年、大阪でスーパー歌舞伎「新・三国志」を観た。特に印象的だった場面の一つは、30㌧の水が降り注ぐ中で大立ち回りを演じた猿之助の甥、市川亀治郎の姿だ。
役柄は関羽の養子・関平。ライトに光る大量の水に全身を打たれながら、戦に死す関羽に向けて自身の決意を力強く語っていた。まぶたの裏に思い浮かべたその場面が今、伯父の名跡を継ぎ四代目猿之助となった姿と重なる。
現在、新橋演舞場で襲名披露公演中。東京まで観劇に行く都合がつかずこの目で見るのは来年の大阪公演となるが、三代目猿之助(現猿翁)が病に倒れた9年前から歌舞伎のことを考えると心も曇りがちだった筆者としては、報道だけで接しても胸が熱くなる。
昼の部は古典歌舞伎、夜の部はスーパー歌舞伎という前代未聞の構成。ハードな内容に反対も多かったが、四代目は「前例がなければつくればいい」と言い切り、実現させたという。その力強い言葉は、三代目が貫いてきたフロンティア精神そのものである。それは現代劇から歌舞伎入りした九代目中車(香川照之)の決心にも通じる。
血縁よりも何よりもまず「市川猿之助」の名を継ぐに必要なのは、「誰もやっていないこと」に果敢に挑む精神。役者にこのような覚悟があればこそ、歌舞伎は単なる伝統芸能ではなく、古くて新しい極上のエンターテインメントなのだ。
「翁の文字身に沿うまでは生き抜かん」と、昨年の会見で三代目猿之助は色紙に書いていた。まだまだ「翁」の文字は身に沿わない、と。その宣言が嬉しかった。永遠の挑戦者、それが「市川猿之助」の精神である。(里)