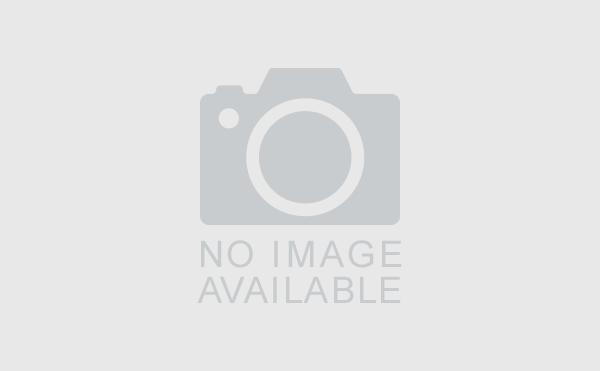台風12号の記録的大雨を受け、県が関西電力に要望していたダムの発電用(利水)容量を活用した洪水被害低減のための新たな運用方法がまとまった。日高川町の県営椿山ダムの場合、従来は放流しなかった利水容量をすべて吐き出すこととし、新たに400万立方㍍を確保。これにより、流入量を100%放流せざるを得なくなる「但し書き操作」に至るまでの洪水調節可能時間は、約1時間40分遅らせることが期待できるという。
台風12号の大雨では椿山ダムのほか、 那智勝浦町の那智川、 新宮市の熊野川などが氾濫。 治水と利水の機能を持つ多目的ダムの椿山ダムは、 長時間にわたる大量の流入により、 流入量をそのまま100%放流せざるを得ない状態 (但し書き操作) に陥り、 県はこのダム機能がなくなる状態を回避、 またはできるだけ遅らせるため、 ダムの治水容量に加えて発電用の利水容量もあらかじめ放流できるよう、 関西電力と協議を進めていた。
その結果、 有田川の二川ダム、 古座川の七川ダムなども含め、 県は最大放流量を最大で約1割低減させ、 洪水調節可能時間を最大で約2時間遅らせることが期待できると説明。 椿山ダムは従来、 治水容量を吐き出した時点の水位が187・6㍍だったが、 利水容量もすべて放流することによって水位が3・6㍍低下。 新たに400万立方㍍を確保、 計画上の治水容量は3550万立方㍍となり、 但し書き操作までの時間は約1時間40分先延ばしできるという。
新たな運用方法は気象台の予報に基づき、 計画規模を超える洪水が予測されるときに県が放流実施の可能性を判断。 県の要請により、 関電が利水容量の水位を低下させる。 今後、 実施要領を作成して関係市町村等への説明、 住民への周知を行い、 6月16日までの運用開始を目指す。
仁坂吉伸知事は11日の記者会見で概要を説明のうえ、 「ダムがない状態 (但し書き操作) をできるだけ遅らせるというのが今回の見直しの意義であり、 こういうものは最善を尽くすことが大事。 住民の逃げ方のシミュレーションなども含め、 日高川は河川の改良も組み合わせて取り組んでいく」と述べた。