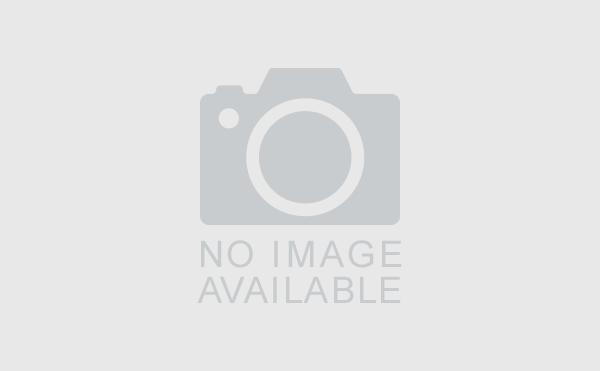新潟県柏崎市の避難所でボタン鍋の炊き出しを行う梅ママ隊
16年前の阪神淡路大震災が発生したとき、マスコミは自衛隊や警察の初動の遅れを批判した。みなべ町西岩代の梅農家尾﨑剛通さん(62)は当時、消防団に所属し、被災地神戸への出動招集がかかるものと思っていたが、町内の活動を原則とする消防団の神戸への出動はなく、テレビを見て自衛隊や警察を責めるマスコミに同調しながら、「批判はしても行動していない自分」に気づいた。消防団という 「組織」とは別に自由に動ければ。しかし、たった1人では目の前の命も救うことができない。身近な仲間に救助隊の結成を呼びかけた。農家が多く長期の活動はできないため、最長でも1週間、災害発生直後に一命をとりとめる人命救助を中心として、平成7年12月、紀州梅の郷救助隊が発足した。
最初の震災の出動は9年後、16年10月の新潟県中越地震。夕方、若手を中心に8人が車2台に乗り込み、12時間かけて被災地の小千谷市へ到着した。通称「マルキン」と呼ばれる緊急自動車通行証の不携行、宿泊先を確保できないなど失敗もあり、結局、人命救助はできなかったが、南海地震に備えて被災地の勉強をするため、新潟には4回出動。がれきの撤去や家のかたづけ、避難所でのもちつきなど、現地で知り合った阪神大震災被災者の女性ら同志と連携し、頼まれたことは何でもやった。この中越地震の経験により、「どこへでも行ける」という自信がつき、その後も能登半島地震(19年3月)、中越沖地震(19年7月)、中国・九州北部豪雨(21年7月)、兵庫県佐用町豪雨(21年8月)など多くの災害に出動した。
いくつもの現場活動でさまざまなノウハウを身につけ、大規模災害発生時には出発前に現地へ先乗り、ニーズを調べてくれる仲間のネットワークもできた。「遠くから早く駆けつけることで、現地の人が勇気づけられる」。しかし、今回の東日本大震災は自分たちの和歌山県にも大津波警報が発令されていた。解除されるまでの間、福島県へ入った救助隊の高砂春美兵庫県支部長から、「原発事故で郡山にボランティアセンターをつくることになった。その準備を手伝ってほしい」という連絡が入った。和歌山の警報解除を待って13日午後、若手を主体に7人がワゴン車で出発した。南相馬市にいる高砂支部長と合流するため、放射能漏れのニュースと余震が続くなか、原発から少しでも遠回りしながら、東北道を北上し、 相馬市経由で南相馬市へ入った。

気仙沼市でがれきの中の遺体を捜索する隊員
これまで経験したことのない放射能の恐怖。目に見えず、においもなく、感じることもできない。福島第一原発では2日前の12日、1号機の建屋が爆発し、この日昼前には3号機の建屋も爆発した。長袖の作業着で肌を隠し、マスクをつけて作業を始めたものの、実際に自分たちがいる場所の放射線レベルはどれだけなのか。錯綜する情報に不安が募る。隊員の中にはまだ結婚前の子もいる。「こんな状態ではとても屋外活動を続けられない」。尾﨑隊長は決断した。ボランティアセンター担当者に「申し訳ないが、ここはいったん引き揚げさせてほしい」と告げた。最前線から初めての撤退。貴重なガソリン10㍑をもらって南相馬を離れた。
北に隣接する相馬市内では、地震で屋根が壊れた家の女性に「何か手伝えることはありませんか」と声をかけ、瓦を下ろしてブルーシートをかぶせる作業を行った。このとき、津波警報のサイレンが鳴った。「放射能の次は津波。でも地震もないのになぜ?」。近くにいた警察官の命令で逃げたが、サイレンは誤報だった。混乱はおさまる様子がなく、みなべへ戻った。
3月25・26日には、女性メンバーでつくる梅ママ隊が新潟県柏崎市の避難所を訪問し、ボタン鍋の炊き出しを行った。2日間で3カ所のコミュニティセンターを回り、計約500食。食材のイノシシはみなべ町岩代地区の猟友会、ホウレンソウやキャベツ、ダイコン等の野菜は印南町羽六地区の住民が提供。往復のバスは田辺観光バスがガソリン代だけで出してくれ、仲間のコーディネーターの女性を通じて、沖縄のJA糸満支店ファーマーズマーケットから30万円の義援金も届いた。ほか、缶詰や梅干し、衣類など、隊員の友人や知人、活動を支援してくれる人たちから多くの物資が託された。コンビニ弁当の食事が続いていた避難所の人たちにとって、身も心も温かくなる最高のボランティアとなった。
震災からちょうど1カ月の4月11日夜、女性5人を含む22人の第3陣が宮城県気仙沼市へ向かった。このときも高砂支部長が先乗りし、避難所の人たちに何をしてほしいか聞いてくれていた。本隊到着を一日千秋の思いで待っていた70代の女性は、津波で家がやられ、連れ合いは行方不明となっていたが、「うちのお父さんは流されていない。きっと家の中で死んでるはず」とすがるように訴えた。メンバーはただちにがれきを掘り返しにかかった。家は倒壊のうえ、火災で全焼。掘っても掘っても見つからない。そのとき、「お前ら何やっとるんや!」という怒号が響いた。関西から応援で来て、被災地をパトロールしていた警察官の声。立ち会っていた女性と地元の社協職員が現場を離れた瞬間、火事場泥棒に間違えられた。「けんかをしている場合ではない」。怒りをこらえて事情を説明、女性が「このへんにあるはず」という場所を探し続け、ご主人の遺骨を見つけた。
被災地で手伝えることはいくらでもある。農業、住職、建設業、運転手、水道工事業などメンバーの職種はさまざま。なかでも多い梅農家はいま、収穫時期で大忙しだが、尾﨑隊長は「1人でも2人でも、きめ細かく被災者のニーズにこたえたい。また、時間があれば行こうと思ってます」という。